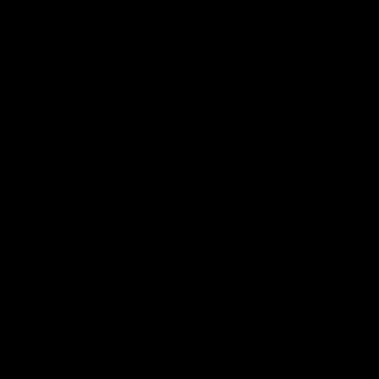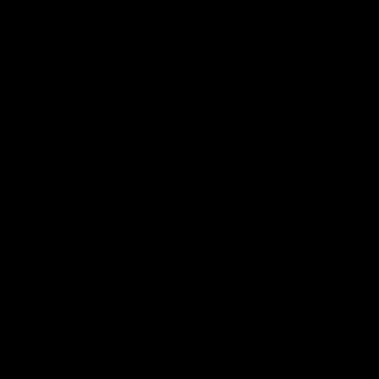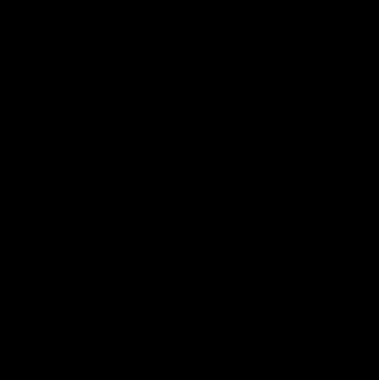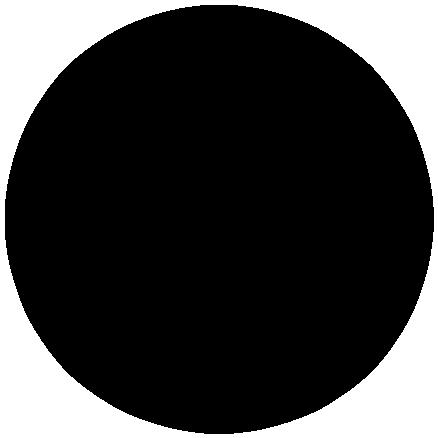日本不動産市場の変革 サステナビリティマーケットサマリー 特集 総集編 vol.1 Research 日本リサーチ | 2024年6月
欧米の環境規制が促す
jll.com
欧米の環境規制が促す日本不動産市場の変革
01
EUタクソノミーの不動産市場への影響 EUタクソノミーとは
EUタクソノミーを支える情報開示制度
02 エンボディドカーボン削減の動き エンボディドカーボンとは
エンボディドカーボンを算出するLCAツール
グリーンビルディング認証とエンボディドカーボン 12 GRESBとエンボディドカーボン
03 日本の現状と課題 エンボディドカーボンとLCA
建物のエネルギー性能評価と省エネ性能表示 15 加速するグリーンビルディング認証取得
本レポートはJLLの定期刊行物「サステナビリティマーケットサマリー」2023年秋号から2024年春号の特集を再 編集したものである。 2
Contents
4
6
不動産セクターの規制
7
8
13
11
14
17

“2023年7月、イギリスの小売事業者 Marks&Spencerがロンドンのウェスト エンド、オクスフォードストリートにある 1929年竣工のアールデコ建築の店舗を 解体して10階建ての複合ビルに建て替 えようとする計画が許可されなかったと いう話題が一部の注目を集めた。不許 可の理由として、エンボディドカーボン 排出量があったとされる。実は、日本 でも同様の理由で外資系企業が移転を 見送るという事例が出始めている。本レ ポートでは欧米を中心に進んでいるエン ボディドカーボン削減の動きおよびその 関連動向について概観する。
3
欧米の環境規制が促す日本不動産市場の変革

EUタクソノミーとは
2023年は世界の平均気温が観測史上最も高い年となり、世 界各地で熱波、洪水、干ばつ、山火事など気象災害が発生 した。EUのコペルニクス気候変動サービスによると、世界 の平均気温は産業革命前(1850-1900年)と比べて1.48℃ 上昇したという。気候変動枠組条約第21回締約国会議 (COP21)において採択されたパリ協定の2℃目標(1.5℃努 力目標)を達成するためには、2050年までに地球のGHG (Greenhouse Gas: 温室効果ガス)の排出量を実質ゼロ (カーボンニュートラル)にすることが必須であり、残された 時間はあとわずかだ。
EUは2020年に、カーボンニュートラルを含む持続可能な社 会・経済への転換策「欧州グリーンディール」の実現に必 要な巨額の資金を民間から誘導すべくEUタクソノミー(サス テナブル投資を促進する枠組みの設置に関するEU規則 2020/852)を採択した。経済活動・事業が環境面で持続可 能(サステナブル)か否かを分類する基準である。2022年か ら順次適用されているが、その適用範囲はEU内の企業に 限られず、EU市場に上場している域外企業、EU市場に非 上場の一定の条件(EU内の純売上高や子会社・支店等)を 満たす域外企業も含まれる。
01
EUタクソノミーの 不動産市場への 影響
4
Contents →
欧米の環境規制が促す日本不動産市場の変革
EUタクソノミーでは「気候変動の緩和」や「気候変動への 適応」など6つの環境目的が掲げられており、このうち一つ 以上の目的に貢献し、かつ、他の目的を阻害しない「DNSH (Do No Significant Harm)」を原則としている。また、各 環境目的について、特定のセクターの特定の経済活動が持 続可能であるか否かを判断するための技術的スクリーニング 基準(TSC:Technical Screening Criteria)が設定されてい る。TSCには、環境目的に実質的に貢献するかを判断する SC基準(Substantial Contribution criteria)とDNSH基準 が明記されており、これらの基準とミニマムセーフガードの 順守を満たすと4要件がそろい、EUタクソノミーに準拠した 経済活動と認められる。2024年3月現在、「気候変動の緩和」 については9セクター101活動、「気候変動への適応」につい ては14セクター106活動のTSCがリスト化されている。
EUタクソノミーの4要件
1
2
3
4
6つの環境目的のうち 1つ以上の目的に貢献する。
他の環境目的を阻害しない。
ミニマムセーフガード
(基本的人権等の尊重)を順守する。
技術的スクリーニング基準(TSC)に 適合する。
EUタクソノミーの6つの環境目的
気候変動の緩和 (GHGの削減)
気候変動への適応 (自然災害への対処)
循環型経済への移行
出所:欧州委員会委任規制を参考にJLL作成
汚染の予防と制御
水と海洋資源の 持続可能な利用と保護 生物多様性と 生態系の保護と回復
5
Contents →
気候変動の緩和
欧米の環境規制が促す日本不動産市場の変革
不動産セクターの規制
EUタクソノミーの対象となる経済活動の特定およびTSCの 策定は現在も進行中であるが、2024年3月現在、建設・不 動産セクターについては、新規建物の建設、既存建物の改修、 設備等の設置・保守・修理、建物等の取り壊し・解体、建 物の取得・所有など、「気候変動の緩和」および「気候変動 への適応」に関して7つの経済活動、「循環型経済への移行」 に関して5つの経済活動がリストに含まれている。
建設・不動産セクターのTSC
環境 目的 経済活動
たとえば建物の取得・所有に関しては、「気候変動の緩和」 のSC基準として、2020 年 12 月 31 日より前に建てられた 建物の場合、少なくともエネルギー性能証明書(EPC: Energy Performance Certificates)のクラス A を取得してい るか、運用時の一次エネルギー需要(PED:Primary Energy Demand)が国または地域内の建築ストックの上位 15% 内にあること等が記されている。
SC基準で言及されている内容(例)
DNSH基準のある 環境目的
7.1 新築建物の建設 PED、気密性・熱性能、ライフサイクルGWPの算出・開示 ②③④⑤⑥
7.2 既存建物の改修 エネルギー性能は大規模改修に適用される要件に準拠、PED ②③④⑤
7.3 省エネ機器の設置・保守・修理 外壁・屋根等の断熱性、窓・ドア・光源のエネルギー効率、 暖房・空調・給湯システム等の効率、キッチン等の節水・省エネ等
7.4 建物内のEV充電ステーションの設置・保守・修理
7.5 建物のエネルギー性能を測定・制御等する機器等の 設置・保守・修理
7.6 再生可能エネルギー技術の設置・保守・修理
7.7 建物の取得・所有
7.1 新築建物の建設
EV充電ステーションの設置・保守・修理 ②
サーモスタット・センシング機器、BAS・BEMS・EMS等、 ガス・電気等のスマートメーター、日射制御可能なファサード・屋根 ②
太陽光発電システム、太陽熱温水パネル、ヒートポンプ、風力タービン、 太陽光発電コレクター、熱/電気エネルギー貯蔵ユニット、 高効率マイクロCHP(熱電併給)プラント、熱交換器/回収システム ②
2020年以前竣工の建物はEPCクラスA(またはTop 15%)、 2021年以降竣工の建物は7.1の基準、エネルギー性能のモニタリング・評価 ②
7.2 既存建物の改修 ①③④⑤
7.3 省エネ機器の設置・保守・修理 ①⑤
7.4 建物内のEV充電ステーションの設置・保守・修理 ①
7.5 建物のエネルギー性能を測定・制御等する機器等の 設置・保守・修理 ①
物理的気候リスクを大幅に軽減する物理的・非物理的適応策、 物理的気候リスクは付録 A リストから特定、 気候の予測と影響の評価、実装された適応策の影響・是正措置等 ①③④⑤⑥
7.6 再生可能エネルギー技術の設置・保守・修理 ①
7.7 建物の取得・所有 ①
3.2 既存建物の改修
3.1 新築建物の建設 建設・解体廃棄物の処理・再利用・リサイクル、ライフサイクルGWPの 算出・開示、建設設計と技術の循環性、二次原材料の使用、使用した 原材料・部品の電子的記録等、 既存建物の改修について改修前の建物を50%以上保存 ①②③⑤⑥
3.3 建物等の取り壊し・解体 解体前にクライアントと合意、解体前の監査、解体廃棄物の処理、 建設・解体廃棄物の再利用等
3.4 道路・自動車道の維持管理 (省略) ①②③⑤⑥
3.5 土木工事におけるコンクリートの利用 建設・解体廃棄物の処理・再利用・リサイクル、建設設計と技術の循環性、 二次原材料の使用、二次原材料の運搬距離、使用した原材料・部品の 電子的記録等
①②③⑤⑥
※DNSH基準の①~⑥は、①気候変動の緩和、②気候変動への適応、③水と海洋資源の持続可能な利用と保護、④循環型経済への移行、⑤汚染の予防と制御、⑥生 物多様性と生態系の保護と回復を表す。
※PED:一次エネルギー需要、GWP:地球温暖化係数、BAS:ビルオートメンションシステム、BEMS:ビルエネルギー管理システム、EMS:エネルギー管理システム、 EPC:エネルギー性能証明書、EPD:環境製品宣言
出所:欧州委員会委任規制を参考にJLL作成
②⑤
気候変動への適応
①②③⑤
①②③⑤⑥
6
Contents →
欧米の環境規制が促す日本不動産市場の変革
EUタクソノミーを支える情報開示制度
EUでは、EUタクソノミーの法制化と同時期に情報開示に関 する法制化も進められた。金融機関や投資家の投資先を規 制するSFDR(Sustainable Finance Disclosure Regulation: サステナブルファイナンス開示規則)と、事業主の事業内 容を規制するCSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive:企業サステナビリティ報告指令)である。いずれ もEUタクソノミーを参照しており、三位一体となってEUタ クソノミーに準拠した経済活動を推進する仕組みとなっている。
これにより、事業者は投資対象の持続可能性を評価したう えで透明性の高い情報を投資家に提供し、金融機関や投資 家等の金融市場参加者から資金を獲得することになる。
不動産セクターにおいては、不動産投資家等がSFDRのも と投資決定のサステナビリティ要素に与える主な悪影響(PAI: Principal Adverse Impacts)を開示するにあたり、GHG排 出等の一般的な指標に加え、不動産投資特有の「不動産を 通した化石燃料へのエクスポージャー(投資の割合)」および 「エネルギー非効率な不動産へのエクスポージャー(投資の 割合)」という指標がある。一方、企業がCSRDのもと「気 候変動」や「資源利用と循環経済」などESRS(European Sustainability Reporting Standards:欧州サステナビリティ 報告基準)の定めるサステナビリティ情報を開示するにあたっ ては、賃貸不動産がグリーンであることも重要な要素となる。
EUタクソノミーと不動産市場の関連図
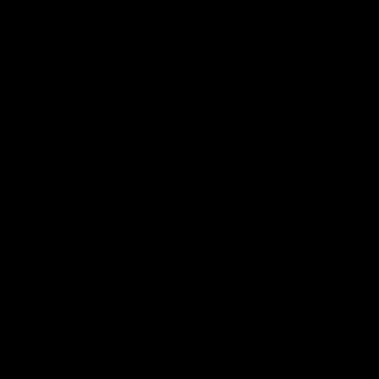
「グリーン」 売上割合を 開示 CSRD (事業ルール)
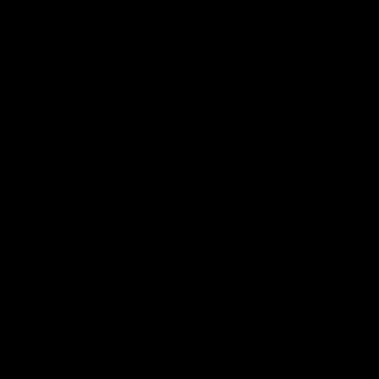
EU タクソノミー
グリーン 企業へ投資
サステナビリティ
開示で資金調達
事業者
不動産関連部署 (テナント)
事業内容に対する ESG説明責任
出所:JLL
「グリーン」の 定義を参照
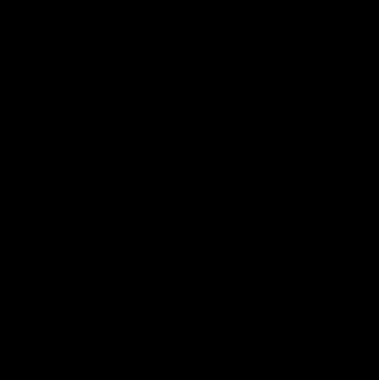
SFDR (投資ルール)
● 省エネ診断
● グリーンビル認証取得
● CRREM Pathwayを用いた省エネ診断
● グリーンビル認証取得
● ESG デューデリジェンス
● EUタクソノミーと国内法規・規制等との 互換性検討
不動産投資家 (オーナー)
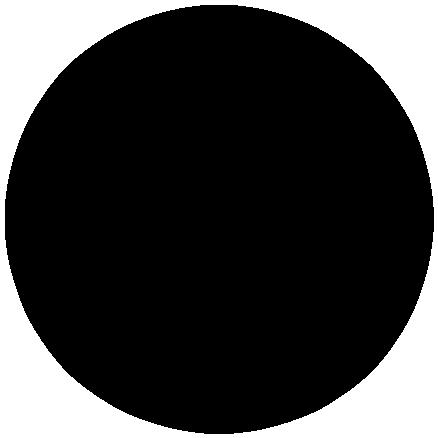
不動産売買の 情報透明性による ESG投資
7
Contents →
欧米の環境規制が促す日本不動産市場の変革

エンボディドカーボンとは
エンボディド カーボン削減の 動き
EUタクソノミーでは、たとえば新築建物の建設における「気 候変動の緩和」のSC基準として、エネルギー性能を一定 程度以上に高めることのほか、5,000m2超の建物の建設に よって生じる建物のライフサイクルGWP(Global Warming Potential:地球温暖化係数)※ をライフサイクルの各段階で 計算し、投資家や顧客にオンデマンドで開示するといったこ とも挙げられている。
気候変動の緩和を実現するうえで、建築物から発生する GHGを削減することは不可避であり、建築物の製造・建設 から解体・廃棄まで建築物のライフサイクル全体を通じて発 生するLCCO2(Lifecycle CO2)の削減に向けた取り組みが 欧州のみならず米豪など複数の国で進んでいる。
LCCO2は、エネルギー消費や水消費など建築物の運用時に 発生するオペレーショナルカーボンと、運用以外の過程で発 生するエンボディドカーボンに大別される。とりわけパリ協 定以後は、オペレーショナルカーボンだけでなくエンボディ ドカーボンの算出を行い、建材の製造・輸送や建設時のエ ネルギー、解体されるまでのCO2排出量も抑制することが 重要であると認識されるようになってきた。実際、2023年 時点で、フランスを含む欧州の複数の国やロンドン(イギリ ス全体ではない)において、建築確認申請時にエンボディド カーボンを算出することが必要とされている。
※GHGが大気中に放出された際に地球温暖化に与える影響力(二酸化炭素の何倍か)を表す数字
02
8
Contents →
欧米の環境規制が促す日本不動産市場の変革

エンボディドカーボン内訳(建築物のライフサイクルで建物運用以外で発生するCO2)
廃棄物の処理 (C�)
原材料の調達 (A�)
中間処理 (C�)
廃棄物の 輸送 (C�)
解体・撤去 (C�)
改修 (B�)
解体段階
工場への輸送 (A�)
資材製造 段階
アップ フロント カーボン
カーボン
使用段階※ (資材関連)
交換 (B�)
修繕 (B�)
維持保全 (B�) エンボディド
施工段階
製造 (A�)
現場への 輸送 (A�)
施工 (A�)
使用 (B�)
※「エネルギー消費(B6)」および「水消費(B7)」など建築物の運用時に発生するCO2(オペレーショ ナルカーボン)は含まない。
出所:令和4年度ゼロカーボンビル推進会議報告書を参考にJLL作成
9
Contents →
欧米の環境規制が促す日本不動産市場の変革
各国・各地域のエンボディドカーボン算定範囲
規制等で定められたエンボディドカーボン算定範囲※
資材製造 施工 使用 解体
原材料の調達工場への輸送 現場への輸送
地域 制度名称
EU EPBD
フランス RE2020
ドイツ QNG/BNB
イギリス Part Z
アメリカ(NY)
維持保全 解体・撤去 廃棄物の輸送 中間処理 廃棄物の処理
Executive order 23 - Clean Construction /Local Law 97 of 2019
オーストラリア Green Star/NABERS
CIC CAT
シンガポール Green Mark
日本 (制度検討中)
※国際規格ISO21930に準拠し「再利用・リサイクル・エネルギー回収による便益と負荷(D)」も境界外の補足情報として算定範囲とする地域もある。
出所: JLL

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 香港
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
10
Contents →
欧米の環境規制が促す日本不動産市場の変革
エンボディドカーボンを算出する LCAツール
エンボディドカーボンを算出するには、LCA(Life Cycle Assessment:ライフサイクルアセスメント)が必要となる。
LCAは従来、温室効果ガスのほか、オゾン層への影響、 酸性化、富栄養化などを対象項目とするものだが、近年、 気候変動が喫緊の課題であるという認識が高まるにつれ、 温室効果ガス、なかでもエンボディドカーボンの検討が重 要視されるようになってきた。
エンボディドカーボンを計算するツールは続々と開発され ているが、欧米やオセアニアでシェアが大きいLCA計算ソフ トウェアとして、OneClick LCA、EC3(Embodied Carbon in Construction)、Tallyが挙げられる。これらの手法は、 国によっては法的な効力をもって建築物設計・施工・運用 段階などで使用されることもあり、建材・什器・機器等の エンボディドカーボンを数値化したデータベースもある。また、 各国の法規制に対応したバージョンが作られているものも ある。
OneClick LCA
概要 建築LCA算定用のソフトウェア
開発者 OneClick LCA社(フィンランド)
特徴
実際に建築現場で使用する個々の資 材データをもとに建設にかかる原材 料調達から加工、輸送、改修、建設、 廃棄時のCO2排出量等を算定できる。
概要 エンボディドカーボン測定用のクラウ ドベースの無償ツール
開発者 北米の建設業界で共同開発
特徴 数千もの建築製品のグローバルデー タベースをEPDから取り込んでおり、 建築見積やBIMから建築資材のエン ボディドカーボンの評価、ベンチマー クが行える。
Tally
概要 BIMソフトウェアAutodesk Revitプラ グインのLCAツール
開発者 Autodesk社(アメリカ)
特徴 建築システムの設計・計画段階でホー ルライフカーボンを評価することがで きる。調達段階ではEC3を用いてエ ンボディドカーボンを最適化できる。
出所: Autodesk、住友林業のウェブサイトを参考にJLL作成
EC3
11
Contents →
欧米の環境規制が促す日本不動産市場の変革
グリーンビルディング認証と エンボディドカーボン
不動産の総合的な環境性能を評価するツールとしてグリー ンビルディング認証制度がある。なかでも世界で最も普及し ているLEED認証は、日本でも250件超の物件が取得してい る。レーティングシステムにより評価内容に多少の差異はあ るが、LEEDは立地と交通手段、水の効率的利用、エネルギー と大気、材料と資源、室内環境品質、革新性といったカテ ゴリーで評価される。現在運用中のv4およびv4.1のBD+C (建物設計と建設)とID+C(インテリア設計と建設)の「材 料と資源」においては、建物の再利用、サルベージ、建物 全体のLCA、EPD(Environmental Product Declaration: 環境製品宣言)を通じたエンボディドカーボンの削減が重視 されている。
また、アメリカではLEED v4(2013年発表、2016年完全移行) 以降、LCAの実施が急速に普及し、近年では設計初期から 3次元モデルを用いた建築物のライフサイクルデータの構築・ 管理が可能なBIM(Building Information Modeling:ビル ディング インフォメーション モデリング)による設計とLCAの 確認を並行して行うことが一般的になっている。その流れの なかで、BIMと建築資材の第三者認証であるEPDを用いた LCAが発展するとともに、多くの建材メーカーがEPDに対応 するようになった。EU各国やオセアニアでも同様の方法が 広まっており、アジアでも徐々に主流になるとみられる。
なお、2024年4月に公開されたLEED v5 BD+C/ID+Cのドラ フトでは、エンボディドカーボンの算出が必須となっている。
カテゴリー
①統合プロセス 1 2
②立地と交通手段 16 18
③持続可能な敷地 10
④水の効率的利用 11 12
⑤エネルギーと大気 33 38
⑥材料と資源 13 13
⑦室内環境品質 16 17
⑧革新性 6 6
⑨地域における重要項目 4 4
配点ポイント合計 110 110
出所: USGBC LEED scorecard をもとにJLL作成
評価項目 BD+C (NC) ID+C (CI)
リサイクル可能資源の 収集と保管 必須 必須
長期間のコミットメント 1
建物のライフサイクル
環境負荷低減 5
内装材のライフサイクル 環境負荷低減 4
製品の環境情報の明示 (EPD) 2 2
原料の採取 2 2
材料の成分 2 2
建設および解体廃棄物の 管理 2 2
配点ポイント合計 (全体ポイントにおける割合) 13 (12%) 13 (12%)
BD+C (NC) ID+C (CI)
LEED
LEED
v4、v4.1 の配点
v4、v4.1「材料と資源」の配点
12
Contents →
欧米の環境規制が促す日本不動産市場の変革
GRESBリアルエステイトと エンボディドカーボン
不動産・インフラ会社やファンドのESG配慮の姿勢を測 るツールとしてGRESB(Global Real Estate Sustainability Benchmark)がある。GRESBはESGパフォーマンスデータ を検証・採点しベンチマーク評価を提供するものであり、投 資家はESGに関する機会・リスク・影響を確認し投資判断 に活用することができる一方、不動産管理・運用者はESG パフォーマンスデータを提出し評価を受けることで改善計画 の策定に活用することができる。GRESBにはGRESBリアル エステイト(既存物件の運用を主とするリアルエステイト評 価と新規開発を主とするデベロッパー評価)およびGRESB インフラストラクチャーがあるが、前者には2023年時点で世 界で2,084社、うち日本から135社が参加している。
パフォーマンス要素の評価
リアルエステイト評価はマネジメント要素30%とパフォーマ ンス要素70%、ディベロッパー評価はマネジメント要素30% とディベロップメント要素70%で評価され、総合スコアのグ ローバル順位により上位20%に「5Star」が与えられる。こ のうちディベロップメント要素では、①ESG要件の「開発中 のESG戦略(配点4点)」や②建材の「建材選択要件(配点 6点)」においてエンボディドカーボンについて言及されてい るほか、②建材に「ライフサイクルアセスメント」や「エン ボディドカーボン」といった指標(いずれも配点は0)がある。 エンボディドカーボンは不動産会社やファンドを評価する GRESBにおいても重要な要素となりつつある。 評価の観点
ディベロップメント要素の評価
評価の観点
マネジメント要素の評価
出所: GRESB Real Estate Reference Guide をもとにJLL作成
配点 ①リスクアセスメント 9.0 ②目標設定 2.0 ③テナントとコミュニティ 11.0 ④エネルギー 14.0 ⑤GHG 7.0 ⑥水 7.0 ⑦廃棄物 4.0 ⑧データモニタリングとレビュー 5.5 ⑨ビルディング認証 10.5
配点 ①ESG要件 12.0 ②建材 6.0 ③ビルディング認証 13.0 ④エネルギー 14.0 ⑤水 5.0 ⑥廃棄物 5.0 ⑦ステークホルダーエンゲージメント 15.0
配点 ①リーダーシップ 7.0 ②ポリシー 4.5 ③報告 3.75 ④リスクマネジメント 5.0 ⑤ステークホルダーエンゲージメント 10.0
評価の観点
13
Contents →
欧米の環境規制が促す日本不動産市場の変革

エンボディドカーボンとLCA
日本の現状と
建物のLCAに関しては、日本建築学会が1990年代から「建 物のLCA指針」の作成を目指し、2003年に初版を公開、そ の後も改訂版を発刊してきた。しかし、計算が煩雑なため 実務で行うことは稀で、広く使用されるに至っていない。一 方、2022年には三井不動産と日建設計が中心となり、同指 針をより実務的に活用しやすいようにアレンジした「建設時 GHG排出量算出マニュアル」を策定した。同マニュアルは 検討会での議論を経て、2023年6月に一般社団法人不動産 協会から「Scope3算定を行う建築工事発注事業者のための 『建設時GHG排出量算定マニュアル』2022年度版」として 会員に配布されるなど少しずつ前進している。
しかしながら、日本では設計段階でのBIM作成が遅れており、 未だ欧米のような方法でのLCAの実施は一般的とは言えな い。また、先述のとおり、One-Click LCAやEC3といった手 法は国によっては法的な効力をもって建築物設計・施工・ 運用段階などで使用されることもあり、建材・什器・機器 等のエンボディドカーボンを数値化したデータベースもある のに対し、日本では建築物設計・施工・運用いずれの段階 でもその計算が義務とされておらず、データベースの整備 も遅れている。
課題 03
14
Contents →
欧米の環境規制が促す日本不動産市場の変革
参照するデータベースがなければ、日本の建材・什器・機 器等を使用した建物のGHG排出量を算出することはできな い。エンボディドカーボンを考慮した建物環境性能の評価が できないとなると、EUタクソノミーを意識する海外投資家に とって日本の不動産を取得・保有することはリスクとなり得る。 やがては日本の不動産は放出され、日本の不動産市場が海 外から取り残される事態にもなりかねない。ゆえに、日本 においても今後急速にエンボディドカーボンの算出が求めら れるのは必至である。
欧米の動きを受け、国土交通省は2022年12月に「ゼロカー ボンビル推進会議」を設置した。IBECs(一般財団法人住宅・ 建築SDGs推進センター)の主導のもと産官学が連携して、 LCCO2(Lifecycle CO2)を実質ゼロにする建築物「ゼロカー ボンビル」の評価手法を整備している。2024年5月にIBECs から公開された建築物ホールライフカーボン算定ツール (J-CAT)は、One-Click LCAとの連携にも配慮が見られ、 また、建材のEPD取得状況が芳しくない現状でも計算できる。 将来的にEPDが拡充された場合にも対応するよう計画され ており、今後の展開に注視したい。
建築物のエネルギー性能を評価する日本の制度 出所: JLL
根拠
評価方法
建築物全体の設計時の 省エネルギー性能を示す制度
非住宅建築物に係る 省エネルギー性能の表示のための 評価ガイドライン(通称:省エネ基準)
地域・建物用途・室使用条件 などにより定められている
「基準一次エネルギー消費量」に対する 「設計一次エネルギー消費量」
建築物のネットゼロエネルギー 到達状況を示す制度
第4次エネルギー基本計画 (2020年までに新築公共建築物等で、 2030年までに新築建築物の平均で ZEBの実現を目指す)
「省エネ」のみでの 一次エネルギー消費量削減率と 「創エネ」を含めた正味の 一次エネルギー消費量削減率
ランク 5段階の星(☆)表示 『ZEB』、Nearly ZEB、 ZEB Ready、ZEB Oriented
建築物省エネ法の2022年改正により、 2025年4月から原則すべての
備考
新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が 義務付けられる
基本的には BELSの5つ星の建築物について、 再生可能エネルギーの導入の 程度に応じた評価が与えられる
制度 BELS (Building-Housing Energy-efficiency Labeling System ) ZEB (Net Zero Energy Building)
概要
15
Contents →
欧米の環境規制が促す日本不動産市場の変革
建物のエネルギー性能評価と 省エネ性能表示
EUタクソノミーでは、建設・不動産セクターの「気候変動 の緩和」のSC基準にエネルギー性能がある。EUを中心と する海外投資家が日本の不動産を取得する場合、EUタクソ ノミーをベースとした取得基準を設定していることも多い。
それゆえEUタクソノミーの日本の法規・基準への読み替え をいかに定義するかが注目されている。同時に、日本のZEB (Net Zero Energy Building:建築物のネットゼロエネルギー 到達状況を示す制度)、欧州のEPC(Energy Performance Certificates:エネルギー性能評価書)、Top15%(エネルギー 性能が国内建物の上位15%)など建築物のエネルギー消費 に対するラベリング・評価・計算方法や、エネルギー性能 を評価項目として含むグリーンビルディング認証への関心が 高まっている。
日本では、2022年6月に「建築物のエネルギー消費性能の 向上に関する法律(通称:建築物省エネ法)」が改正され、 2025年4月から原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基 準適合が義務付けられるとともに、2024年4月から「建築 物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」が施行されるこ ととなった。非住宅建築物の省エネ性能ラベルにはエネル ギー消費性能が6段階の星印(6つ目は太陽光発電自家消 費分)で表示され、再エネ設備の有無や、太陽光発電の売 電分も含めてエネルギー収支がゼロ以下を達成した場合に は「ネット・ゼロ・エネルギー」であることも表示される。
これにより、不動産を購入・賃借する当事者は省エネ性能 を踏まえた物件選択が可能になる。
しかし、議論が当初より後退し、ラベル表示が義務付けら れるのは2024年4月以降に確認申請を行った物件のみで、 2024年3月以前に確認申請を行った物件(既存建築物)につ いてはラベル表示を推奨するにとどまった。海外投資家にとっ て投資の判断基準となる明確な指標・表示がないことは、 投資意欲を損なわせ、日本の不動産に流入する海外資金を 減少させ、日本の不動産の新陳代謝を悪化させかねない。
今後、既存建築物にもラベル表示が義務付けられ、既存建 築物のエネルギー性能の向上、さらには、日本の不動産市 場の好循環につながることを期待したい。

16
Contents →
欧米の環境規制が促す日本不動産市場の変革
加速するグリーンビルディング認証取得 欧米の環境規制が厳しくなるなか、日本においてもグリーン ビルディング認証の取得が加速している。不動産関連事業 会社は、自らが宣言したESG情報開示に説得性を持たせる ため、自社が所有する不動産に対しLEEDやCASBEEなど のグリーンビルディング認証を取得するようになってきた。
不動産管理運用会社に至っては、運用する不動産の総資産 価値に占めるグリーンビルディング認証を取得した不動産の 資産価値の割合によってGRESBの格付けが左右されること から、グリーンビルディング認証の取得が不可欠となっている。
GRESBについては2024年以降、認証取得からの年数が得 点に反映されることとなり、今後ますます既存建物の認証 更新が活発になると思われる。
また、欧州の投資家や彼らの委託を受けて資産を運用・管 理をするAM会社が日本の不動産の改修や取得を検討する
場合、グリーンビルディング認証取得に加え、CRREM ※ (Carbon Risk Real Estate Monitor)を用いた省エネ・脱炭 素診断も必ず話題となる。欧米の環境規制の強化、不動産 の性能評価の世界標準化という潮流から日本も逃れること はできない。実際、CASBEEのSランクを取得した不動産で もCRREM Pathwayで座礁するケースが多発しており、こう いった不動産への投資が鈍化することが懸念される。LEED では同様の事態に対応すべくOptimize Energy Performance (エネルギー性能の最適化)の配点を厳格化してきた(詳細 はJLL「 サステナブル不動産への道:エネルギー編 」参照)。 日本においても国内法を整備し世界基準との互換性を高め ることが急務である。JLLでは、投資家向けのコンサルティ ング業務でKPI(Key Performance Indicator:重要業績評 価指標)を設定して説明を行うにあたり、自社オフィスを設計・ 施工する際の目標としてLEED等のグリーンビルディング認 証を用いている。世界の動向に機敏に対応することは企業 の強みとなるだろう。 SDGs(Sustainable Development Goals)
投資家
事業会社
出所: JLL
責任投資原則
TCFD
気候関連財務情報開示 タスクフォース
SBTi
科学的根拠に基づく目標 イニシアティブ
再生可能エネルギー���% イニシアティブ
不動産サステイナビリティベンチマーク
※欧州の機関投資家を中心に開発された、個別の不動産や不動産ポートフォリオの気候変動リスクを分析するツール。
会社 不動産 ESG投資 ESG情報開示 CASBEE DBJ-GB BELS LEED BREEAM WELL GRESB PRI
RE���
不動産管理運用会社
17
Contents →
欧米の環境規制が促す日本不動産市場の変革
エナジー&サステナビリティサービス事業部(ESS)のサービス
専門技術スタッフ
全世界で1,000名以上のサステナビリティ 専門のスタッフが連携対応
ESG戦略策定/開示基準/
気候変動リスク
• 戦略策定(TCFD、SFDR、TNFD、SBTi、 Resiliency etc.)
• 開示報告(Energy、GRESB etc.)
• 脱炭素(CDP scores and modules etc.)
• 脱炭素・省エネ診断
• データ管理
• ベンチマーキング
• コミッショニング
• CRREM分析
• 運用管理アドバイス
サステナビリティデザイン
• LCA/エンボディドカーボン計算による アドバイス
• 設備設計コンサル
• プロジェクトマネジメント
ビル認証取得/ESG DD
• LEED、WELL、fitwel
• CASBEE、BELS 脱炭素診断
■ オフィス ■ ホテル ■ 店舗 ■ 工場 ■ 住宅 ■ 公共施設 ■ 研究所 ■ 物流施設 脱炭素・ 省エネ診断
120件以上の診断を実施
データ管理
■ 事業会社 ■ 上場REIT ■ 私募ファンド
国内省エネ法やGRESBに必要な データ管理支援を1,000件以上実施
JLLは不動産に関する多種多様なサステナビリティサービス・ソリューションを提供しています。
お客様に最適な不動産サステナビリティ戦略の構築・実現を支援します。
18
Contents →
欧米の環境規制が促す日本不動産市場の変革
JLLが東京・大阪で LEEDとWELLをダブル受賞
~ LEEDとWELLのシナジーを利用 ~
JLL本社オフィス(東京)は、2023年3月にLEED v4 Interior Design and Construction: Commercial and Interiorsで最高ランクの「プラチナ」認証を取得した。国内で当該カテゴ リーのプラチナ受賞はトヨタ自動車のPowertrain Building No.3 Officeに次ぐ2例目である※。 また、2023年9月にはWELL v2 pilotで最高ランクの「プラチナ」認証を取得した。インテリ アプロジェクトでのダブルプラチナ受賞は国内初である。
JLL関西支社オフィス(大阪)は、2023年9月にLEED v4 Interior Design and Construction: Commercial and Interiorsで上から2番目のランクの「ゴールド」認証を取得した。大阪で の当該カテゴリーのゴールド受賞は初である※。また、同月、WELL v2 pilot で最高ランクの「プ ラチナ」認証も取得した。当初はゴールドの取得を目指していたが、東京オフィスに近い水 準のウェルネス環境を整えたことで、プラチナに到達した。
※USGBC公開プロジェクトリストによる
LEEDプラチナ取得のポイント(東京)
01 立地、エネルギーおよび水のカテゴリーで 高得点を狙えるビルを選定
02 ベースビルの潜在能力に加え、プロジェク トの設計でも省エネルギーな照明や超節 水器具を選定(一部共用部の器具も交換)
03 これまで比較的難しいと言われていた 材料系の項目にも挑戦し獲得
04 v4で取得の難しいAcoustic Performance も得点
WELLプラチナ取得のポイント(東京)
01 LEEDと共通する項目(シナジー)を利用
02 世界共通で使用されるJLL社内規定によ り、ダイバーシティや従業員のウェルネスに 資する項目を獲得
03 水質、空気質、音響、温熱などの測定によ る項目を全て取得
04 取得の難しい材料の項目についてもLEED とのcrosswalk(類似項目達成により自動 取得)により得点
19
Contents →
松本 仁
エナジー & サステナビリティ サービス事業部⻑ jin.matsumoto@jll.com
お問い合わせ先 ジョーンズ
東京本社 〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町1-3
東京ガーデンテラス紀尾井町
紀尾井タワー 03 4361 1800
JLLについて
渡部 まき
エナジー & サステナビリティ サービス事業部ディレクター maki.watanabe@jll.com
⾚城 威志
リサーチ事業部⻑ takeshi.akagi@jll.com
剣持 智美
リサーチ事業部マネージャー tomomi.kemmochi@jll.com
関西支社 〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜 3-5-29
日本生命淀屋橋ビル 06 7662 8400
JLL(ニューヨーク証券取引所:JLL)は、不動産に関わるすべてのサービ スをグローバルに提供する総合不動産サービス会社です。オフィス、リテー ル、インダストリアル、ホテル、レジデンシャルなど様々な不動産の賃貸借、 売買、投資、建設、管理などのサービスを提供しています。フォーチュン 500®に選出されているJLLは、世界80ヵ国で展開、従業員約108,000名 を擁し、2023年の売上高は208億米ドルです。企業目標(Purpose) 「Shape the future of real estate for a better world(不動産の未来を拓 き、より良い世界へ)」のもと、お客様、従業員、地域社会、そして世界を 「明るい未来へ」導くことがJLLの使命です。JLLは、ジョーンズ ラング ラ サール インコーポレイテッドの企業呼称及び登録商標です。jll.com
福岡支社 〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅 2-20-1
大博多ビル 092 233 6801
JLLリサーチについて
名古屋オフィス 〒450-6321
愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1
JPタワー名古屋21階 052 856 3357
JLLリサーチは、世界のあらゆる市場、あらゆるセクターにおける最新の 不動産動向並びに将来予測を提供します。全世界550名超のリサーチエ キスパートが、60ヵ国を超える国々の経済及び不動産のトレンドを日々 調査・分析し、世界のリアルタイム情報と革新的考察を発信しています。 グローバル、リージョン、そしてローカルの不動産市場におけるエキスパー トが集結する精鋭リサーチチームは、今日の課題、さらに将来の好機を も特定し、競争上の優位性、成功のための戦略、不動産に関する最適な 意思決定へとお客様を導きます。
JLLリサーチは、適正な市場メカニズムが機能する公正・透明な不動産 市場の形成に寄与することを使命とし、より良い社会の実現に貢献します。
This report has been prepared solely for information purposes and does not necessarily purport to be a complete analysis of the topics discussed, which are inherently unpredictable. It has been based on sources we believe to be reliable, but we have not independently verified those sources and we do not guarantee that the information in the report is accurate or complete. Any views expressed in the report reflect our judgment at this date and are subject to change without notice. Statements that are forward-looking involve known and unknown risks and uncertainties that may cause future realities to be materially different from those implied by such forward-looking statements. Advice we give to clients in particular situations may differ from the views expressed in this report. No investment or other business decisions should be made based solely on the views expressed in this report.
Copyright © Jones Lang Lasalle IP, Inc. 2024
jll.com
ラング ラサール株式会社