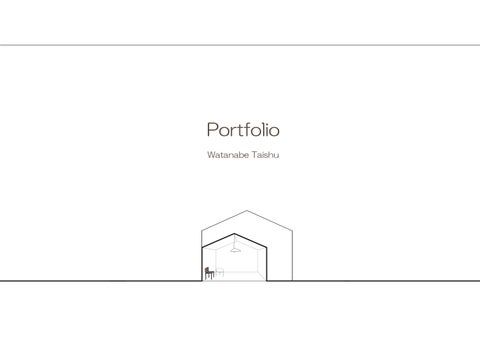Portfolio
Watanabe Taishu
WATANABE TAISHU

大阪市立大学大学院 生活科学部研究科 居住環境学コース 修士2年 渡部 泰宗 1997年 大阪府堺市生まれ 2020年 摂南大学 建築学科 卒業 竹原義二・白須寛規 研究室 2023年 大阪市立大学大学院 生活科学研究科 小池研究室 修了見込
01,卒業設計 「断片に宿る懐かしさ」
受賞歴
掲載作品 摂南大学建築学科 卒業設計
02,木の家設計グランプリ 2021 「キトケイハウス」
せんだいデザインリーグ
03,第9 回 POLUS 学生・建築デザインコンペティション 「庭をつくり変化を楽しむ新たな暮らし方」
04,第 14 回ハーフェレ学生デザインコンペティション 2022
「敷地境界を無くした世界」
05,第 10 回大東建託賃貸住宅コンペ 「Share Life」
木の家設計グランプリ POLUS 建築デザインコンペ ハーフェレ学生デザインコンペ
大東建託賃貸住宅コンペ
06,修士設計 「ニュータウンの 20 年計画」
大阪市立大学大学院 修士設計
07,課外活動 「学部偏・修士偏」
最優秀賞 100
優秀賞・横内敏人賞 入選 選外佳作 3 位 最優秀賞 2020 2021 2022 2023
選
卒業設計 B4
無人駅の駅舎という空間の魅力 。 そこにはいろいろな背景があ り 人の
記 憶、 思いがそ こに はた くさ んあ ると 感じ る。 普 段 都 市の中に い る私
た ちにとっ て、 誰 も がそ の 空間に親 し みを抱 き、 魅 力 的 だ と感じる 何
かがそこにはある。一度も訪れたことがないような場所がなぜか懐かし いと感じてしまう。そんな魅力を秘めた無人駅の駅舎であるが、その一 方で収益の少ない負の財産となっている。利用者の数も年々減り続けて
おり、年 に1 路線は廃線となっているのが現状である。今回設定した

敷地も4年前から6番目の廃線予定とされている駅舎であり、街の高齢 化によりいずれ廃線となる。しかし、昔懐かしいと感じるような場所、
空間を亡くしてしまってはいけないと思う。そこで、 近 年増 加し てい
る無 人駅 に対 し て、街の懐かし風景の断片から構成された新たな駅舎 空間を提案する。
学内卒業設計展 最優秀賞 せんだいデザインリーグ 全国100選
01,断片に宿る懐かしさ ~街の断片から構成された新たな駅舎空間~

が置かれていた
電柱とミラーが近くに並んで置かれて いるようだ キレイにそぎ取られた木の束 鉄骨の棒が立ててある










伝統的な木構造でつくられた天井























錆びた鉄骨の柵が並んで置かれている









街中に手すりの部分がある。自然な道 をつくる。
積まれている
の窓が景観とつながって見える。




















ドア枠が空間をつくりだす






引き戸の鴨居と白い壁の組み合わせ 天井壁がなく、木構造 を意匠として見せる ベンチと壁の関係 電柱や大きさバラバラな箱が並んでいる ホームの下部分が鉄骨の軸を組んで台を支えている 因美線が廃線になれば路線は このような風景が残る 小屋の間にフレーム部分だけが 残ったエレメントがあった 建物を軸組とつなぐ天井 屋根材は波板版 ホームのコンクリートの塊とポ ツンと置かれた小さな建物 門で入口ができている。その真ん中に小さ な切符入れ。 段差の階段が緑に埋もれている 柱とコンクリートの地面 柱の存在 網状に組まれた仕切りと布材料で上部分を隠している 石積になっている壁に小さ な段差がくっついている 廃虚となった木造の小屋と、そ
段差が境界線を作ている ように思える 田舎の緑道とその周りには田
電柱橋と柵が前後で重
道のそばに鳥居の形をした木組
の中に自販機が置かれている
んぼが広がっている
なっている
格子状に窓が連続して並んでいる。木造の駅舎特有
3段しかない段差がつけら れている 窓縁の前に柱
杉の木の丸太が束になって
小屋の待合室に4つの椅子 が横並びしている 木で組まれた構造に波板壁と屋根で 覆われた建物 木造の軸組と白壁の対比関係 縦線の入った白い壁と屋根 那岐駅の駅舎内風景。ベンチや、
だ 塩ビ波板の素材で壁が作れている 小さな木の小屋の下に色んなものが置かれ ている 岩とその周りは砂利が敷かれている コンクリートの地面と電柱 森の中に囲まれた小屋が建っている。 キレイにそぎ取られた木の束 鉄骨の棒が立ててある ホームと庭の領域を 分ける木組みの柵 昔ながらの長屋のファサード 看板やポストが特徴的 箱が二つ並んで置かれている 門と屋根が組み合わさる構 造となっている 廃虚になっている駐輪場の場所 道とつなぐ橋 街に知らせを伝えるたえに使わ れていたものが残っていた 街のシンボルとなるような街の 看板の役目をになっている 屋根でおおわれた空間を線路との繋が りを和らげているようだ 今は使われていない小道具が、置かれ ていた。昔を思い出すエレメント 小さな木のブロックが通路を分ける効 果を持たせている 街の中に棚が置かれてあり、 その中にいろんな本がある 机やいすが集まって空間 をつくっていた ミラーと電柱がセットで並べられている 看板やはしごが壁に置かれて あった 使われていない線路が残っていた ホームの看板が懐かしい風景の 断片となっている 街の看板。その横に小さなこの が置かれている。 木造壁の板が連続的並べられいた
電柱とミラーが近くに並んで置かれているよう
カタチの方法論


懐かしさはエレメントに宿る (出会い方・組み合わせのデザイン)
ただ増築をして用途を与えるのではなく、空間を形づくるエレメントというものに着目し、建築をつくっていく。設計手法として、建築やその周辺 に偏在している部分を拾い上げ、その要素で構成する。方法としては敷地調査時に懐かしいなと感じたものを写真としておさめ、集めた写真の要素

で建築をつくっていく。敷地調査時にとってきた写真から考察し、そこからくる構図をヒントに形を構成していく。8つの敷地があるのだが、それ ぞれ増築の仕方や改修の表現は違う。しかし、街の懐かしい要素という部分同士が相対化される構図は常にあって、それが全体の構成となっていく。 ◇部分の考察から得た構図をヒントに






◇エレメントの挿入とその接続部分



❶ ❷ ❸ ❻ ❹ ❺ Methodology of the form
壁に閉ざされており、 とても暗い空間になっ ていた。ここを開放的 にさせる
大空間の階段空間を 演出させるためにも 壁部分は解体させ、 柱だけをエレメント として入れる


ここの壁を街の要素を取 り入れるために部分的に 木材のフレーム部分を断 片的に挿入させた

伝統的な木造の柱梁の構 造は残しつつ、改修をお こなっていく。天井部分 は解体させる


ホームの段差をここの 階段空間に断片として 入れた。街の小さな風 景を取り入れる。



N
図書ギャラリー 図書スペース 談話スペース ギャラリー 形の方法論 階段の活用 まちのライブラリー 既存平面図 待合室 便所 駅長室
Planning 既存を残し増築する 那岐駅
Diagram
出会い方のデザイン
街の中にあったベンチや、手すり部分、柵の躯体といったものを エレメントとして抽出し、そのエレメントどうしの出会い方、組 み合わせ方をデザインし、設計に持っていく。何パターンもの組 み合わせがうまれ、その決定手段について規則性というものはな く、断片というもののエレメントが構造になったり、時には空間 の意匠として使われながら、街の部分を駅舎空間に作り上げたかっ た。建築の創作のなかに時間性というものを考え、空間を形づく るエレメントの関係性に注目している。この建築は、すべての時 間を一元化せず、バラバラのまま並存させるために、あらゆる雑 多なエレメントを無数の時間の表象として等価に捉えながら、そ
れらの膨大なエレメントの関係性をつなぎ合わせている。
Design of the encounter
壁と柱部分をくっつける














新たな壁を挿入











木サッシの構図














新たな柱壁の挿入 縁に合わせて重ねた


木造駅舎の単体 木造駅舎の単体 駅舎内にある木のフレーム 木のフレーム 木材の板壁 周辺の倉庫の木組み構図 鉄フレームの構図 駅舎の木組みの エレメント 鉄筋フレーム 既存の壁材料 小屋の壁部分 構造部材を重ねる 壁の木軸フレーム 混在させてみた 木造駅舎の単体 鉄筋フレームの軸組 木の門の構図 木造駅舎の単体 鉄筋フレーム 木造駅舎の単体 鉄筋フレームの躯体 木造壁の既存部分 壁の縁だけを 持ってきた 内部に挿入されている 駅舎の待合空間 駅舎の待合空間 駅舎が小さな小屋に 壁と鉄フレームの 出会い方 壁と電柱の 出会い方 街の神社の鳥居 連続した板壁 木の軸組構図
木材の板壁 箱の壁に木造壁を
壁の縁だけを 持ってきた 既存の壁との重なり
外部空間と内部の空間 窓サッシの構図 隣合わせて壁となる
小屋の屋根部材 木で組んだ構図
鉄材の軸組
つなげていく
によってデザイン
間に鳥居構図を置く
ホームの段差
木造壁フレーム 鉄骨躯体 新たな壁の挿入 つなげ合わせる 部分が箱をつくる 雑多な部品が 組み合わさる ホームの電柱 を構図に持ってくる 少しズレをつくり 空間を仕切る 少しのズレをつくる 一部分だけつなぎ 合わせる 鉄筋フレーム 新たな壁・白 木サッシ 木サッシの構図 新しい白壁部分 木の軸組構図 角度を振って 壁となる 木造駅舎の単体 鉄材の軸組 木造駅舎の単体 手すりのフレーム 木造軸組みの壁 駅舎ホームの段差 二つの関係性を考察 木造駅舎の単体 エレメントを重ねる 手すりを隣合わせて 周辺敷地の柵部分 重ねてみる 壁の代役 重ね合わせて 倉庫の壁材使用
街の要素を活かしたまちづくり計画
対象敷地は鳥取県と岡山県をつなぐ 無人駅の駅舎であり、この街はすで に廃線になった駅舎や無人駅が多く 点在している。今回設定した敷地は 8駅連続した無人駅である。この通 過点に過ぎない各駅舎の個性を拾 い上げ改修を行っていく。
設計手法は、空間を形づくる エレメ ントというものに着目 し、建築をつ くっていく。方法としては敷地調査 時に「懐かしい」と感じたものを 写 真としておさめ、その集めた写真か ら断片を考察し、形を構成する。街 の部分が全体の構成をつくり出し、 様々な用途の8駅が連続に繋がる ことによって、1つの街の観光ス ポットができる。

岡山県 津山市

一泊二日の旅の企画


AM8:00 宿泊施設

1
PM12:00 ギャラリー空間
1
AM18:00 あば温泉
1
AM10:00 街の小さな図書館
1
AM12:00 休憩所
1
AM14:00 展望台




1
PM16:00 記念館
1
PM18:00 駅舎マルシェ
展望台 街の広場 街の小さな図書館 ギャラリー空間 宿泊施設 休憩所 記念館 駅舎マルシェ あば温泉 直売所 娯楽施設 めぐみ食堂 レストラン 桜の名所 美術館 ※各駅舎の用途は変更可能 自転車 因美線 地域資源スポット
断片に宿る懐かしさ















~断片から構成された新たな駅舎空間~

電車移動が必要



駅舎で一泊することが可能












街の懐かしい部分の断片により 街の部分を 見ている かのような空間となる。







ここを出発点として旅は始まる。




次のスポットに向かっていく 旅を終えていく。


街の自然を感じながら、およそ 30分かけて歩く。
※各駅舎の用途は変更可能

なくなっている空間が生まれ変わっていく






木造駅舎の格子窓を取り 付け、インテリアはノス タルジックな空間に。 鉄骨の躯体部分を一部増 築の部材として持ってく る。 かつてはお店だった廃虚 の建物の小さな看板を 持ってくる。 手すりや柵だったものを そのまま形のエレメント として挿入する。 屋根部分を軽い素材を使 う。仮設建築として、自 由に形をつくる。 小屋が物置になっている 原理で増築をする。小ス ケールのものから大きさ はそれぞれ マルシェ 共有スペース 高野駅 N 街の中にあった倉庫建築 で、増築の部分を柱と屋 根躯体でつなげていた。 駐輪場倉庫の躯体部分、 波板の壁を壁の要素とし て使っている。 手すりの部分であったも のを構造体として持って くる。 仮設建築の躯体部 分を材料として使 う。 駅舎や川辺付近ではよく 砂利が多くみられた。内 部ではあるが要素を使う。 新たな壁のエレメントと して持ってくる。白い壁 が木造壁と対比する。 記念館 待合室 駅舎の木造壁と格子窓の1枠 だけをエレメントとして持て くる。 ここから窓をのぞき込むと、 きれいな景観を見れるとい う。絶景スポットとして位置 する。ここから覗き込んだ場 所の記憶として残るだろう 街の電灯を持ってきて壁の隣 にただ置かれたエレメント。 ここから窓をのぞき込むと、三浦駅から見れる津山市 の街を美しい景色が見渡せる。 N 待合室 N この駅舎の周辺にあった、 鳥居の構図を駅舎の構造 としてつかう。 古びた壁を新たな壁とし て改修する。既存部分の 木造壁はそのまま残す。 格子窓が特徴的なので、その ままこの場所にもてきた。こ こから光を取り入れる。 この街は、因美林産業が 盛んな地域。杉の木の丸 太を構造でも利用する。 部屋を開放的にするため に、窓や開口部の部分の 窓枠を付ける。 待合空間 休憩所 ベンチをそのまま持って くる。駅舎の雰囲気はそ のまま残す。 伝統的な木構造の柱、梁 は既存のまま。主に壁や 一部柱梁が改修される。 扉部分を既存部分の待合 空間の内部のエレメント をここにもってくる。 街の要素を部分的に取り 入れる為に、古びた壁を 新たな壁として改修する。 砂利の要素と、岩が意匠 として機能する。壁は木 造のまま使う。 宿泊 エントランス 寝室 街中にある、木でつくられた ベンチを入れる。地面は砂利 がひかれている 路地裏空間の要素を取り 入れ、街の小さな風景を 展示室に取り入れる ここの部分は窓を開放的に 開けるために、木の枠で囲 みながら窓をつける。 ギャラリーの展示空間の 場所を街の要素を取り入 れるために、地面に砂利 をひく。 木造壁の部分は解体せず に残しつつ、内部にも挿 入させていく。 駅舎の木造壁と新たなエ レメントの壁が組み合わ さる ギャラリー 展示 展示スペース 展示スペース N ここの壁を街の要素を取り入 れるために部分的に木材のフ レーム部分を断片的に挿入さ せた 伝統的な木造の柱梁の構造は 残しつつ、改修をおこなって いく。天井部分は解体させる 壁に閉ざされており、とても 暗い空間になっていた。ここ を開放的にさせる ホームの段差をここの階段空 間に断片として入れた。街の 小さな風景を取り入れる。 大空間の階段空間を演出 させるためにも壁部分は 解体させ、柱だけをエレ メントとして入れる 図書ギャラリー 図書スペース 談話スペース ギャラリー 街の要素から持ってきた ものがここに使われてい る。 コンクリートの地面と、 小さなポストが場に風景 をつくりだす。 ホームの段差を置いて、 椅子になったり、子供た ちが登って遊ぶ場所に。 木や、釘とロープでつく られたものを広場で使わ れる。
土師駅 高野駅 美作加茂駅
知和駅 美作滝尾駅
三浦駅 那岐駅 美作河井駅
街の広場 街の小さな図書館 ギャラリー空間 宿泊施設 休憩所 展望台
記念館 駅舎マルシェ
それぞれ 街に適した用途を与え、使われ
駅舎と因美線の 街が一体となる提案
無人駅の駅舎が 街のシンボル となってゆく
木の家設計グランプリグランプリ2021 M1
02, キトケイハウス
コンペテーマ:「コロナ時代に考える職住一体の住まい」

Concept:
私たちは学校帰りの夕焼けを見て天気や時間の変化を感じ たり、朝会社に向かおうと外に出た時の肌寒さから季節の 移り変わりを実感してきた。一方でコロナ時代の現在は外 出自粛やリモートワークによって家の中で全てが完結し、
そういった自然環境の変化を感じる機会が減っているよう
に思う。自然環境の変化は暮らしの中の行動に大きく影響
を与え、単調な生活にも些細な彩を添える要素であり、コ ロナ時代の中にも必要なものであると考える。
優秀賞・横内敏人賞・10選(/209作品)
~木が時間を教えてくれる住宅~

枝葉の 間を通り抜ける光の粒
木漏れ日 風の揺らぎ
◇木がもたらす変化の多様性
木の下の空間は完結せず、地面に陰を落とせば、人の居場所が生 まれる。風の揺らぎ、枝葉を通り抜ける光の粒、樹木の形はいつ も違った表情を見せ、自然環境の変化を私たちに教えてくれる。
◇太陽の動きと働く場の変化
木陰の大きさや動きは季節によっても異なる。夏の陰は小さく、長い時間落ち ているのに対し、冬の陰は大きく短いといった違いがある。時間によって変化 する木の陰と共にお店の働く時間や活動領域も変化する暮らしを提案する。
:働く時間 :働く空間 S 夏至:日の出 夏至:日の入り 春分・秋分:日の出 春分・秋分:日の入り 冬至:日の出 冬至:日の入り N 夏至 職空間の大きさの変化 職空間の時間の変化 31° 55° 78° 冬至 春分・秋分 大 小 長い 短い
影の輪郭と職空間


木の葉は雨の雫を伝って流れ落ち、屋根の形態も 雨の水が流れ落ちていく有機的な屋根をかける。
シンボルツリーであるクスノキは 照葉樹であるため、内部に光を取 り込みやすいような形態とした。
平面と断面のズレにより内外に連続性が生ま れ、風や光といった自然環境と溶け込んでいく。
Aʼ A 2800 1400 4500 7250 道路境界線 道路境界線 公園 2960 3040 2650 6600 3300 4600 2300 2800 3050 3160 3160 N 3250 土間 1FL±0 1FL-600 1FL-1200 家族室 居間 キッチン 厨房 玄関 洗面所 テラス ひろば(ベーカリー) 中庭
◇形の方法論 ◇視線の抜けによる角度 木 時計 解体 輪郭 屋根 ボリューム N 緑 公園 池 道 線路
水 光 風 動線
アクソメ図
玄関から太陽の木漏れ日が降り注ぐ中庭をみる。
ロフト空間から屋根の天窓の景色を眺める。 屋根から伝ってきた雨水をみながら自然を感じる。





クスノキは長寿の木であり、木の成長と共に 家族構成や使われ方も変化する。
影を取り込む連続戸
空や自然の風景を切り取るピクチャーウィンドウ
屋根の 間から光を取り込む三角屋根
2000 1420 最高高さ:GL+ 風 土間 玄関 中庭 風 ▽1FL:GL+150 △GL±0 △GL±0 ▽1FL:GL-960 3570 3260 960 2200 1890 3760 3120 640 1500 1000 5100 11360 150
第9回POLUS学生・建築デザインコンペティション M2
~人や街をつなぐ「器」となる庭のような建築群~
コンぺテーマ:「終わらない家」
Concept:
これまでの住宅は、人中心に街がつくられてきた。それに よる社会的な影響は大きなものとなっている。今回は建築 や都市の終わりをむかえないよう、新たな暮らしを再考す る。これまでの建築計画を一度否定するかのように、公私
を反転させた庭を主体とした住まい方を提案する。庭が主 体で、戸建はサブ的なもの(専用<共用)にすることによ り、人の暮らしと切り離されていた自然と寄り添い、更新
的に足し引き可能な建築群を構築する。絶えず変化する自 然が暮らしに介入し、暮らしだけでなく、人や街も繋がっ ていくことを目指す。

入選(5選/539作品)
03, 庭をつくり変化を楽しむ新たな暮らし方

Concept:「庭」を主体とした住宅群の暮らしの提案
これまでの住宅は一戸建てに「庭」設け、自然環境を附属的に付け備えていた住まいであり、その集合で街が出来上がっている。しかし、 今回提案するのは戸建て付き「庭」の建築である。庭的な建築の集合ができることにより、空間を共有する場が多様に生まれ、庭を介し て人や街が繋がってゆく、コミュニティが出来上がってゆく。
「庭」付き戸建て住宅 戸建て付き「庭」住宅
Diagram「カタチの方法論」:外部空間から建築をつくる
庭のような建築をつくるため、建築の方法は内部空間からつくる設計方法ではなく、外部空間からつくる建築の方法論を試みましたあくまでも
完成した建築形態をつくらずに、あえて完結していない余白をデザインすることで、時間とともに使い手が思い思いに生活をつくっていきます。
庭をつくる
住居部分は最小限に計画 建築の操作 外部環境 完成 庭のような建築群 半屋外で暮らすデッキや テラスピロティ空間
3mのグリット上に 建築を落とし込む計画
完結させない建築を目指して ー断面ー





プライベートの住の機能は最小限にし、4人
プライベートの住の機能は最小限にし、4人
家族が住む大きさに住宅を設計している。
家族が住む大きさに住宅を設計している。
居住1
居住1
陽当たりの良い場所でテレワークをする風景
共用部が街に開かれ、 街のダイニング空間に。
共用部が街に開かれ、 街のダイニング空間に。
ダイニング
ダイニング
風 台所スペース
完結させない建築を目指して ー断面ー 風 中庭空間 台所スペース
庭のデッキのように将来的に増築可能な余白を


居間のような場所が街に開かれるこ とで、街の居間の空間へと変化する。


街の居間 動 静 中庭空間 風
居住2 木陰の下で読書をする人。中庭から共用部を見た風景 1階のピロティ空間がリビング空間として使われる風景
つくり、完結させない空間をつくり出す。


第14回ハーフェレ学生デザインコンペティション M2
04,敷地境界を無くした世界


~モノやコトの集積でかたちづくられる都市の新たな風景~
コンペテーマ:「パラレル・ユニバース」
Concept:
我々が住む街には無数の線に囲われた均質な境界線の領域が存在する。決められた線どう しが生活を限定させ、個性のない画一化されたくらしをつくってしまう。街の境界線を一 旦ゼロにした瞬間、広い世界が見えるはず。無数の境界線を再編集し直し、街の個性を取 り戻す。それはモノ(所有)が領域をつくり出すパラレルユニバースの世界である。


選外佳作




家具スケールが透過に分散 敷地境界を無くし , 最小限の箱をつくる イメージ配置図兼平面図 S=1/220 リビング空間からみた、広場のコモンズ空間 まちの多様な居場所空間 トップライト LDK 寝室 玄関 マイチャリ テラス 木の下でお昼寝 子供部屋 広場 まちのリビング 寝室 寝室 寝室 ダイニング 0 2 4
から、新たに生命を取り戻すつくり、個性を無くしていた街家具やモノ、建築や人が境界をくことだろう。それは塀や庭、がない風景へと生まれ変わっていは時間の経過とともに見たことしまう。解き放たれたその街まった制約を一旦リセットして界線がつくり出している凝り固たまちとは言えない。敷地境均質化された街や都市は生き




モノやコトの集積から生まれる森うに見えてまとまり合っている、をつくり出し、一見バラバラのよがバラバラに、かつ計画的に領域持ち物)といった雑多なスケール界はほとんどない。モノ(家具・でが私の場所といった明確な境こなしており、どこからどこま一体を自分の家かのように住みる光景を目にした。彼らは街なように空間を共有し合っていい思いに居場所をつくり、好き街がある。そこでは住民達が思とある街に敷地境界を無くした の中の世界のようである。



~
第10回大東建託賃貸住宅コンペ アイデア提案部門 M2

05, Share Life
コンペテーマ:「賃貸住宅とSDGs」
あなたのSGDs考:
SDGsの誰一人取り残さないをテーマに、「11.住み続けられるまち づくりを」の項目を重点に置いて考えました。日本において、特に人 口減少・高齢化の流れが大きくなっていく中、住宅地の空家や老朽化 が深刻化しています。本提案敷地は私が生まれ育った大阪堺市が舞台
になっており、今後のニュータウンの未来がどうなるのかをSDGs に照らし合して考えました。私が思う「10年20年先もずっと住み続
けられるまち」とは、小さなつながりが途切れることなく、地域の中 でお互いが支え合える関係性があるまちだと思います。本提案では、 それらを新しい仕組みで実現させることを考えました。
3位(/165作品)
~街の拠点となる新たな街区モデルの提案~
れた空地が地域の拠点へしていく。また、提供さ改修レシピで小さく改修ニュータウンならではの地を有効活用するため、において、空き室や空き宅が多くなっている郊外単身高齢世帯の持ち家住 と変えていく。




ShareLife A
り出すことができる。が暮らしを自在につくあえて設計し、住み手は完結しえない環境をしている。内部だけで地の新たな建ち方を示い建て方が、郊外住宅小限の賃貸住宅の小さにする。また、この最せ、2つの敷地を1つ敷地境界をスッキリさ
♨
スマホのApplication(アプリ)で便利に住みこなす ち寄れる場をつくっている。にし地域の人がふらっと立1階レベルをピロティ空間げるキッカケ装置となり、ユニットが人と人とをつなシェアキッチンやサブスク 希薄化したニュータウンの 街を少しずつ変えていく。

スマートフォンのアプリケーションと連動させることによって、まちに 点在するサブスクユニットがマップ上に表示される。ユニットは基本街 区拠点に配置されているが、出張サブスクユニットがまちの必要な場所 まで向かってくれるサービスも備わっている。例えば、福祉を必要とす
る高齢者には、アプリ機能で、サブスクユニットが駐車場まで来てくれ
るサービスも導入されており、入浴・食事・ランドリー等が利用できる。
アプリ内のマップを見ながらユニットがどこに配置されていて、何のサー
ビスが稼働しているのかを、スマートフォン1つで簡単に確認できるよ うに住民に情報公開することで、地域全体で守り使っていく。
径半 内圏m052 コ ミ ュ ニ テ ィ 単位
◆ 小学校に変わる新たなコミュニティの拠点
半径250m単位の範囲内で成り立つコミュニティネットワークを構築させるための街区のモデルをデザインする。

文 文 コミュニティ単位 ・従来の近隣住区論の概念図 文 コミュニティ単位 ・新たなコミュニティモデル 凡例 街区公園 (半径250m範囲) 凡例 近隣公園 コミュニティの拠点(Share Life A) 小学校 A D C B
◆ 新しいコミュニティ単位のマップ図 ~「新」近隣住区論~
槙塚台地域会館 槙塚台小学校 250m コミ ュ ニ テ ィ 位単
街区モデルの波及化
MSL-B
MSL-C
MSL-A (槙塚台ShareLife A)
◆ 最小限賃貸ユニット+サブスクユニット
空家が増える郊外住宅地に対して、新しい住まい方のモデルを構築させる。それは「くらしのサブスク化」である。これまで、 土地を所有し、その範囲内で暮らしが完結していたが、これからはより多様な住まい方や働き方を許容できるような新しい住ま いが求められるはず。そこで、建築(既存)を小さくつくってしまい、外部がないと成立しない居住環境(最小限賃貸住居)を想定し、 減築をおこなう「生活のアウトソース化」。
既存の建築を小さくする事の社会性と新しい建ち方・建て方を提案する。
多様な働き方、多様な住まい方を許容できるように新しい賃貸料の形を考える。各街区に対し、賃貸料+サブスク料をもらう ことで多様な空間やサービスを受け取ることができる。また、街区外の周辺住民(半径250m範囲を想定)にもサブスク料だ けのサービスも利用可能にする仕組みをつくる。

空家の活用 最小限賃貸ユニット サブスクユニット アプリに登録 住 生活のアウトソース化 住民(持家) ♨ + 色んな人がサービスを 好きな時に利用できる public private 道路 敷地 (事例1) 最小限住居
◆「暮らしのサブスク」による共同体
体制表と事業スキーム
まちのコミュニティ・関係図
(※半径250m圏内を想定したサービス設計)
~空き室・空間の利活用ネットワークの構築~
◆ Application(アプリ)内のレシピコンテンツ
アプリ化(無料公開) 減築・解体レシピ
地域住民
空き(室・空間・土地)の提供
街区内の住民
空き空間
謝礼金
企業支援 テナント料金
売上げの数%
サブスクオーナー (主婦・若者)
売上収益
企業したい人が気軽に始められる
拠点外の周辺住民
サービスの利用
情報・連携
支援金
アプリと連携
コミュニティ拠点
DIY改修の感覚でアプリを活用 入居 収益
管理人 (NPO法人)
核となる拠点 「最小限賃貸ユニット」
地域イベント参加 ・ボランティア
サブスクユニット
開発 実装 ¥
槙塚台ShareLife A
+
運営支援
街区内(拠点)の住民
徒歩圏内(250m)範囲のサービス設計
今後、空家や空き室の数が増加する事を考慮して、今あるモノを活かしたまちづくりが必要になってくる。そこで、街区拠点を核としたコミュニティネットワークを構築させる。
アプリを活用し、空家や空き室を地域の拠点場に変える仕組み。例えば、街区内で提供してもらった空地にサブスクユニットが入ることで、近隣住民の若い人から高齢者まで 徒歩圏内(250m範囲内)でサービスが利用可能となる。また、この仕組みが成り立つ鍵は街区モデル内(MSL)の住民である。そのため
拠点内の住民はサブスクを割引・
無料でサービスを受けられる仕組みにし、「便利でお得が身近にある生活」のメリットを提供する。この関係図が今後の住み続けられるまちへと変えていく核となる。
利用時間・料金 ShareLife会員(サブスク料金 )
○○円 ○○円 ○○円 月額料金/月 入浴券・セット 入浴セット無料 キッチン無料 10枚/月 付与・無料 20枚/月 付与・無料
無料 無料 無料 洗剤セット 利用券・Myカップ 朝食券・キッチン利用 サブスク料金表 ¥
営業時間9-19時
10枚/月 付与・無料 20枚/月 付与・無料
♨
【 改修(減築・付加・解体)レシピ 】 【 サブスクユニット 】 ※レシピは随時アプリ内で追加・更新される 減 付加 解 a b c d e f g h 1階をスケルトン 2階空間の利活用 屋根を残し内部の空洞化 仮設的に付け加える 既存の壁を有効活用 擁壁を無くし 敷地境界が拡がる 築 体
◆
国・行政の支援 企業の支援 入居者 (学生・単身世帯) ¥ ¥ ¥
補助金
空きの活用 ¥ ¥ ¥ ¥
割引で使用可能 (一部無料) ♨
MSL-A拠点
時間をかけて作り上げた最小限住居が完成すると移住者が住まうための住居拠点ともなる。
ら、建築と街のカ タチを少しづつ変えてい
限の住居。分解と移築を繰り返しなが
建築家である私が、ニュータウンの郊外住宅地に入りな
がら、新たな「コミュニティモデル」を時間をかけてつ くりあげる、ある1つのプロジェクトを示した設計提案で ある。近隣住区論によってつくられた郊外住宅地(ベッ トタウン)では、働く場所がなく、かつ近隣センターは もともとお店・人が集う場所であったが、いまでは空家 がほとんどである。そこで、本提案では郊外住宅地に新 たな拠点をつくり、コミュニティの核をつくり直す新し い仕組みを、本設計で提示することを目指す。
既存のカタチを一回バラバラに分解することで、終わってしまった生命 をもう一度新たな生命へと吹き込む行為を分解手法と名付ける。 象徴的に
1 室だけを残した最小
ジーを形成させるための廃材の再構築をおこなう。
分解プロセスのなかに、建築の生態 系の循環 エコロ
最小限住居を建築しながら、周辺のまちも同時につくっていく、建築を創 る事と街をつくる事が一体となったまちづくりの在り方を実践している。

最優秀賞
大阪市立大学大学院 終了設計 M2
06, ニュータウンの20年計画
~郊外住宅地における新近隣住区の設計提案~
露天風呂 ユニット化され た檜小屋 既存の木材を 再利利用 基礎コンクリートの増設 煙突 テラス 階段 リビングカフェ テラス ステンレス パンチング波板 ステンレス金網 テラス 前庭 パーゴラ 1,820 ハイカウンター :合板 厨房テーブル:集成材 キッチンユニット
木造の戸建て住宅を減築改修させ、最 小限の豊かな暮らしをデザインする。 生活インフラをまちにアウトソース化 させ、地域との生かし合いのネットワー クを移住者は体験する。
「ニュータウン20年計画」 ニュータウン再編プロジェクト
公園に対して背を向けていた建ち 方からつながりを持たせるよう に、裏庭部分にテラスを設けるこ とで、建ち方を逆転させる。


築50年以上の建物であり、今はもう建て壊しされる 予定の建物。既存の建物を生かした改修を考える。



RC造でつくられたモダンな建物の戸建て住宅。 この建物の一階部分をキレイに改修させ、地 域に開けた銭湯へとリノベーションさせた。
1階部分を地域に開かれたコミュニティスペースにコン
バージョンさせ、南側にキッチン付きのまちのダイニン グ空間となるコワーキングスペースを増築させた。

コミュニティ単位
移住者は地域のサブスクユニットを体験するため、PM2時 にリビングカフェへ向かい、地主さんとお話をしながら、 テレワークを行う場所としても利用する。


増改築を繰り返し、築50年以上ということもあ り開発当時の姿かたちを継承されている建物。
近隣住民が集える場所がニュータウンにはほとんどないため、介護のケ アを受けられる場所を設けると同時に、地域住民が集える場所を設ける。 2件の 間に計画された集会所ユニットで井戸端会議が始まる。
建築家がまちに入り、ニュータウンの閉じた箱として孤立している街を 少しづつ段階的に「まち」と「人」との新たな結合関係をつくっていく。 「生かし合いのまちづくり」をコンセプトにプロジェクトを立ち上げ、 閉じた住宅街を対象に、小さく、また、できる範囲内で街に開く仕組みをつくり、 会話のきっかけとなるような装置の集積をデザインするところから 生かし合うコミュニティは形成されていく。
♨ 職住一体住宅 空家・空き地 移住者 (関係人口) 近隣住民 (街区内) 半径100m
半径100m範囲の新近隣住区の暮らし
お風呂のサブスクユニット 1階部分の水回り部分を大きめに改修し直し、まち に開放する。そうすることで、まちの小さな公衆浴 場となり、地域に開放しない時は家族がいつでも大 浴場を利用できるといった移住者にも、近隣にも、 そして地主家族にもメリットがある。またここが、 災害時でのまちのシェルターの役割も果たす。
計画地 : 住宅の「浴室」 用途変更: なし (浴室⇒小浴場) 既存構造: RC造 改修内容: 住宅の浴場部分を大きく スケールを上げ、地域の人に小さく解 放させる計画とする。




既存構造: 木造2階建て 増減部分: 木造一部鉄骨造 改修内容: 空き室となっている一室 空間をまちに開くように改修させ、同 時に塀部分もスッキリさせる。

エキスパンドメタル
リビングのサブスクユニット 家のリビングと言えば、家族団欒の場所であり、ひ とりで居てもいいし、誰かとつながりも持てるフレ

キシブルな場所でもある。そんなリビング空間の要 素がユニット化され、そこをコワーキングスペース で利用されたり、ご飯を食べるダイニング空間にも なる。 平面図1/200 断面図 S=1/50
計画地 : 住宅地の「前庭」



既存構造: 木造2階建て
増減部分: 木造一部単管パイプ
改修内容: まちとの接続関係をつく るために、前庭部分の塀を解体させ、 そこに新しくパーゴラを設ける。
小さな公衆浴場
※移築改修の事例を一部抜粋
平面図1/200 ステンレス パンチング波板 ステンレス金網 テラス ダイニング 前庭 パーゴラ 500 3,200 3,740 04. 井戸端ステーション 1,320 バルコニー手摺り:
S=1/50 階段 広場 風 49.74 16.0 まちの小さな公衆浴場 露天風呂 ユニット化され た檜小屋 既存の木材を 再利利用 基礎コンクリートの増設 煙突 既存RC造 テラス 断面図 S=1/50 移築・増築部分 既存部分 テラスバルコニー 平面図1/100 平面図1/100 テラス 廊下 階段 リビングカフェ 木製引き戸 再利用部材「引き戸」 柱:Stパイプ 計画地 : 住宅の1F空き室
01. 02. リビングカフェ
キッチンのサブスクユニット 空いている駐車スペースに簡易的なユニットが挿入 される。週に2回ほど、ご近所さんのママ達で料理 教室を開きながら、周辺の住民もふらっと立ち寄れ るよう小さく開かれる。パンを焼いたり、地元で取 れた野菜で料理をつくったりしながら、興味がある 人どうしのコミュニティが少しずつ、緩やかに拡がっ ていく。
計画地 : 住宅地の「駐車場」 既存構造: めっき鋼板・RC土間 増減部分: 木造 改修内容: 既存の駐車場の屋根をい かし、新たなにキッチンユニットを付 加させる。






休憩所ユニット ニュータウン内のバス停の待合所は看板しかなく、 待つ場所としては少し寂しい。もう少し待つ事や休 憩することに付加価値を与える居場所のデザインを 考える。看板や電柱のエレメント、周辺の自然環境 と調和させるために、シンプルな屋根をかけそれと 繋がったベンチ空間を設ける。
計画地 : 緑地・空き地 既存構造: 更地・基礎部分



内容 : 空き地や緑道に簡易的な 居場所をデザインする。空家で不必要 になった部材を組み立て、移築させる。
スロープユニット ニュータウンは高低差が多いまちであり、坂や階段 が多いことが課題でもある。高齢者も多く、住みや すいまちとは程遠い。そんな不便さをプラスにする デザインを考える。ここで紹介しているユニットは 屋台がスロープと同化しており、散歩のルートとも なるような場所に屋台が流動的に配置される。
集成材 槙塚台4丁 700 3,480 200 柱:再利用部材 で組み立てる 既存の階段 2,400 スロープ 屋台 2,300 3,260 一定期間空地の場所を地域の 人が集える場所へ 910 ハイカウンター :合板 厨房テーブル:集成材 キッチンユニット
※移築改修の事例を一部抜粋
増減部分: 木造一部鉄骨造
平面図1/125 平面図1/50 07. 06. 原っぱ駐車場 S=1/25 S=1/50 S=1/50 S=1/25 3480.0 3480.0
05.
キッチン ユニット 原っぱ駐車場
平面図1/100 平面図1/200
課外活動~学部偏~ 摂南大学 竹原・白須 研究室
竹原義二の最後の黒板授業 ~斉藤助教授の家 清家清(1952)~

竹原先生は、先生としてだけでなく「建築家」として、 学生と常に真摯に向き合い、時に和気藹々と時に緊張感 を持って、 「建築と向き合うこと」「建築の楽しさ」
「建築の偉大さ」を、その姿勢をもって教えてください ました。過去の建築とその時代を読み解くことを通して “建築と社会の関わり”の大切さを学びました。
これが竹原先生が摂南大学を退官される最後の黒板授業 となり、「建築とはなにか」を私たちに最後、対話をな してながら教えてくださる貴重な時間でありました。
制作期間:約2か月 発表日:2019.2.3
竹原研究室で戦後住宅研究を行い、清家清の「斉藤助教授の家」の住宅を調べていきました。本の資料や図面などを読み取り、この 建築が竣工してから68年が経った今も残され続けている意味や背景、日本の住宅の基となる部分を研究を通して学んでいきました。



最後は、書き上げた図面をもとに竹原義二先生と一対一での対面講義をし、住宅建築の本来の考え方、建築の本質を体験する良い機会

となりました。建築の時代性や歴史というものが今の現代建築に大きく影響を及ぼし、深い関係性があるということを知りました。


研究室で長く使われていた本棚をリノベーションし、研 究室の空間が明るく楽しい場所へと生まれ変わらせよう
と始まったプロジェクト。経費は20万という予算の中で
いかにローコストでかつ斬新なアイデアでもって空間を
魅力にするのかを計画段階から実施、DIY作業といっ
たモノづくりの一貫を体験した。たとえ家具1つだとして
もそこから新しい風景をつくりだし、人々を元気にする
ことを学んだ。

設計~制作期間:約半年 完成日:2021.11.14 制作者:渡部・周(研究室)
課外活動~修士偏~ 大阪市立大学大学院 小池 研究室
研究室リノベーション ~伝統工法を駆使した本棚DIY~
キッチンの形が角度を振ることによる 余白のたまり場をつくる。


2020年のコロナウイルスによる
影響でプロジェクトの活動は活 発に行うことが難しくなったな か、本プロジェクトにおいては、 小さくても何かを実験として 行っていくをコンセプトに研究 室内で新しくキッチンを配置し たいといういきさつから本棚作 製による研究室のリノベーショ ンプロジェクトが始まった。コ ストをおさえ、かつリノベーショ ンによって研究室の空間を生ま れ変わらせるために様々な工夫 を凝らしてデザインした作品で ある。
(渡部泰宗)
①新材(EMARFの加工技術)



デジタルファブリケーションの技術を使い、自分たちのデザインを具体化させる。


描いた図面をEMARFのルーターの機械までデータを送り、その材料が手元まで届く。



くさび止めほぞつぎ 打ち付けつぎ 十字相つぎ



デジタルファブリケーション加工(EMARF)
収納スペース・物置

研究室本棚 S=1/100 2021.3.11 平面図 783 1545 1810
大机 再利用部材の展開図
旧本棚の記憶を継承 新たな本棚が空間をリノベーションする
入口側の展開図
平面の配置計画 展開図のデザイン検討 記憶部材の検討スタディ
課外活動~修士偏~ 大阪市立大学大学院 小池 研究室
駅舎ギャラリーイベント
卒業設計でお世話になった敷地、岡山県津山市の因美線
が通る街の、ある1つの集落を対象に、毎年行われる地域
イベントに参加し、そこで駅舎を使った卒業設計の模型
を展示させていただきました。

この駅舎はとても古い建物で、地域からずっと愛され続
けてきた場所です。因美線の路線も6番目の廃線予定とさ
れているローカル線であり、いつかはこの場所も廃線駅 舎になってしまうかもしれない。しかし、この場所がず
っと愛され続ける場所として使われていくためにこの展 示を通して少しでも多くの人にこの街のこと、駅舎のこ とを知っていただく機会をつくりたいと思い起こしたPJ となります。
~卒業設計案の実施プロジェクト~
展示期間:2023.11.5~11.6




課外活動~修士偏~ 大阪市立大学大学院 小池 研究室

泉北ニュータウンに約2年間、研究からプロジェクト、
TAや授業等を通して、修士の期間ほぼ泉北地域に入りな がら、地域の方々と関わり、プロジェクトも起こしてい
く。その中で感じる、まちづくりの難しさも痛感した。
まちづくりは1人でできるものではなく、地域の方々と
の多くの意見交換から生まれる信頼や責任感等をもって
して、お互いの関係性を育みながら、まちおこしをして
いく。そして、プロジェクトを実施していく上でも共に
切磋琢磨する仲間の存在も欠かせないものであるという
ことにも気づかされた。最終的に地域の方々が喜んでく
ださる姿を通して、難しさや苦労の先に、希望や喜びが
あることを学んだ。
泉北ニュータウンPJ 「たよる場」 ~設計プロジェクトマネジメント~
活動期間:修士の2年間 研究・PJ・TA・授業・インターン
地域発表会 泉北まち歩き 地域のヒアリング調査 槙塚台ハロウィンイベント








Fin